行政書士試験-独学学習プラン
行政書士試験-独学学習プラン
■はじめに
おすすめの学習法は、解説本・肢別問題集・基本書を繰り返すオーバーラップ学習法です。
法令科目の勉強の順番は、憲法、民法、行政法、商法の順が効率的です。特に、行政法は憲法や民法の学習後の方が理解が早いと思います。 また、商法も民法の知識があった方が理解が深まります。以下、この順序で学習プランを紹介します。
なお、以下の学習プランの中に登場する参考書の特徴は、行政書士のおすすめ参考書でも詳しく紹介しています。
■憲法
憲法は、判例と条文に尽きる。
まずは、郷原豊茂の憲法 まるごと講義生中継 をどんどん読み進める。
この参考書は、判例が詳しく説明されており、憲法はこれ1冊で十分であると断言できるほどの内容である。
本書を読むときは、覚えようとせず、内容を理解することに努めること。
をどんどん読み進める。
この参考書は、判例が詳しく説明されており、憲法はこれ1冊で十分であると断言できるほどの内容である。
本書を読むときは、覚えようとせず、内容を理解することに努めること。
そして、1分野を読み終えたら、すぐに一発合格 行政書士肢別問題集〈平成21年度版〉 (行政書士一発合格シリーズ) で知識を確認する。
この問題集は、1問1答形式で問題が掲載されており、短時間の知識固めに最大の威力を発揮する。
「郷原豊茂の憲法 まるごと講義生中継」で1分野を読み終えたら、すぐに行政書士肢別問題集で知識の確認をすることが重要である。
で知識を確認する。
この問題集は、1問1答形式で問題が掲載されており、短時間の知識固めに最大の威力を発揮する。
「郷原豊茂の憲法 まるごと講義生中継」で1分野を読み終えたら、すぐに行政書士肢別問題集で知識の確認をすることが重要である。
次に、基本書に知識を集約する。基本書については、定評のあるものなら何でもよい。基本書を読んで、肢別問題集で間違えた知識、忘れそうな重要事項にアンダーラインを引いていく。 アンダーラインは鉛筆で引く。復習を繰り返していくうちに、完全に覚えた知識のアンダーラインは消していくためだ。
最後に、「行政書士肢別問題集」で間違えた問題、及び基本書で重要な事項とされているがまだ覚えきれていない知識をカセットテープに吹き込む。 吹き込むときの注意点は、きれいに録音しようとは思わないことである。多少の言い間違え、録音の順序など気にする必要はない。 覚えなくてはならないことを、片っ端から録音していく。このカセットテープは通勤・通勤時間などの隙間時間で繰り返し聞くようにする。 そして、学習が進んで復習の量が増えてきたら、2倍速で聞くようにする。この学習法で、全範囲の復習を短時間で行うことが可能になる。
これで、1日の学習は終了である。
そして、翌日の学習は、前日までの復習から始めること。前日だけの復習ではなく、必ず前日までの復習を終えてから、次の範囲に進んで欲しい。 つまり、前・・・前日→前前日→前日の復習をすべて行うのである。
具体的な復習法であるが、[行政書士肢別問題集」で既習範囲のすべての問題を解く。問題を間違えたり、理解が不足していると思えば、「郷原豊茂の憲法 まるごと講義生中継」や基本書の該当個所も読む。
前日までのすべての復習をすると、確かに時間がかかる。しかし、同じ範囲を繰り返し勉強しているうちに、当たり前になってくる知識も増えて、復習のスピードはどんどん上がるので、思ったよりは時間はかからないはずだ。 むしろ、1ヶ月後、2ヶ月後にまとめて復習をする方が、時間がかかる。前日までの復習を毎回する方がはるかに効率的である。 最終的には、「行政書士肢別問題集」で問題を見た瞬間に解答・解説が思い浮かぶレベルまで到達することが目標である。
まとめると、
「郷原豊茂の憲法 まるごと講義生中継」で内容理解→「行政書士肢別問題集」で知識の確認→「基本書」で知識を集約→カセットテープ録音→翌日に前日までの復習(「行政書士肢別問題集」で既習範囲すべての問題を解き、間違えたら基本書に戻って徹底的に確認)
という流れで進める。
このように同じ範囲を何回もオーバーラップしながら覚えていく(オーバーラップ学習法)。
■民法
民法は、とにかく1通り回すということが大切である。多少わからないことがあっても、先へ先へと進んでいく姿勢が民法を制覇するコツである。
まずは、行政書士講義生中継 民法 (行政書士一発合格シリーズ) を読み進める。この参考書は、事例を多く紹介しながら説明しているので、理解がしやすい。
を読み進める。この参考書は、事例を多く紹介しながら説明しているので、理解がしやすい。
あとは、憲法と同じである。「行政書士 講義生中継 民法」で内容理解→「行政書士肢別問題集」で知識の確認→「基本書」で知識を集約→カセットテープ録音→翌日に前日までの復習、という流れで進める。
■行政法
行政法は、行政書士試験の中で最も重要な科目である。行政法を得意にしておけば、合格へ一気に近づく。 よって、他の科目よりも力を投入すべきである。
行政法は、法律用語や概念が難しい。そこで、まずは行政法入門 を読み、行政法に特有の法律概念を理解する。
この参考書は、唯一おすすめできる行政法の入門書である。
具体例が多く、難しい法律用語や概念も丁寧に説明されているので、行政法について深い理解が得られるはずである。
を読み、行政法に特有の法律概念を理解する。
この参考書は、唯一おすすめできる行政法の入門書である。
具体例が多く、難しい法律用語や概念も丁寧に説明されているので、行政法について深い理解が得られるはずである。
上記本を読み終えたら、行政書士講義生中継 行政法 (行政書士一発合格シリーズ) で行政書士試験用に知識をカスタマイズする。
で行政書士試験用に知識をカスタマイズする。
あとは、憲法と同様である。「一発合格 行政書士講義生中継 行政法」で内容理解→「行政書士肢別問題集」で知識の確認→「基本書」で知識を集約→カセットテープ録音→翌日に前日までの復習、という流れで進める。
■商法
商法も他の科目と同様である。解説本は、行政書士講義生中継 商法・会社法 (行政書士一発合格シリーズ) をおすすめする。
をおすすめする。
「行政書士講義生中継商法・会社法」で内容理解→「行政書士肢別問題集」で知識の確認→「基本書」で知識を集約→カセットテープ録音→翌日に前日までの復習、という流れで進める。
■多肢択一式対策・記述式対策
多肢択一式対策については、法律用語や概念を文章の中で覚えていくことが大切である。 オーバーラップ学習法は、解説本・基本書を何度も何度も読み込みながら知識を増やしていく。オーバーラップ学習法を実践すれば、多肢択一式問題に対応できる力が自然と身につくはずである。
次に、記述式対策だが、記述式といっても、問われている知識は択一式と何ら変わらない。よって、必要以上に恐れる必要はない。
記述式で問われているのは、条文、論点、手続きの流れなどの基本的な知識である。 しかし、ただ知識を知っているだけでは駄目で、事例に即して知識を運用する力(法的思考力)が求められている。
このような法的思考力を身につけるためには、知識の暗記だけではなく、知識の理解が必要不可欠となってくる。 記述式問題は、「やみくもに知識だけを丸暗記をしてくる受験生は、合格させない」という試験委員からのメッセージなのである。
オーバーラップ学習法は、知識の暗記のみならず理解を重視した学習法である。 理解→暗記→理解→暗記を繰り返していくので、 コツコツとオーバーラップ学習法を実践していけば、特別な対策をしなくても記述式問題に対応できる力がつくはずである。
そして、択一式問題で8〜9割正解できるようになったら、記述式対策の参考書を購入することをおすすめする。
記述式対策の参考書を使う目的は、どこに注意して記述式の勉強をすれば良いのかを把握することである。 くれぐれも、記述式対策の参考書を使って知識を覚えようとしてはいけない。知識の理解と暗記は、解説本・基本書・肢別問題集で行うこと。
記述式対策の参考書で、記述式で問われそうな個所を把握したら、基本書で該当個所をチェックしていく。 この頃には、択一式で8〜9割正解できるほどの実力がついており、ほとんどの知識は既に覚えているはずだから、時間はそれほどかからないであろう。
記述式では、不正確な知識は役に立たないことを肝に銘じて、正確な知識を徹底的に叩き込む。 そして、一度は自分で書いてみること。実際に書いてみると、記憶の不正確さに気づくはずである。 自分の弱点に築いたら、あやふやな知識がなくなるまで、知識の正確なインプットとアウトプットを繰り返すこと。 また、漢字の間違いにも注意して欲しい。
このように、オーバーラップ学習法をベースに、正確な知識のインプットとアウトプットを繰り返して勉強していけば記述式問題も恐れるに足らない。
■一般知識
一般知識の過去問だけは早い時期に1年分くらいは解いておいて欲しい。 というのも、一般知識(特に文章理解)は短期間で力をつけにくいため、あまりにも得点できていない場合は、早々に勉強を始める必要があるからだ。
具体的な学習法は、基本書を読んでから過去問を解くというオーソドックスな学習法でよい。あとは、予備校の模試や予想問題を活用しながら、対策を進めていって欲しい。
おすすめの学習法は、解説本・肢別問題集・基本書を繰り返すオーバーラップ学習法です。
法令科目の勉強の順番は、憲法、民法、行政法、商法の順が効率的です。特に、行政法は憲法や民法の学習後の方が理解が早いと思います。 また、商法も民法の知識があった方が理解が深まります。以下、この順序で学習プランを紹介します。
なお、以下の学習プランの中に登場する参考書の特徴は、行政書士のおすすめ参考書でも詳しく紹介しています。
■憲法
憲法は、判例と条文に尽きる。
まずは、郷原豊茂の憲法 まるごと講義生中継
そして、1分野を読み終えたら、すぐに一発合格 行政書士肢別問題集〈平成21年度版〉 (行政書士一発合格シリーズ)
次に、基本書に知識を集約する。基本書については、定評のあるものなら何でもよい。基本書を読んで、肢別問題集で間違えた知識、忘れそうな重要事項にアンダーラインを引いていく。 アンダーラインは鉛筆で引く。復習を繰り返していくうちに、完全に覚えた知識のアンダーラインは消していくためだ。
最後に、「行政書士肢別問題集」で間違えた問題、及び基本書で重要な事項とされているがまだ覚えきれていない知識をカセットテープに吹き込む。 吹き込むときの注意点は、きれいに録音しようとは思わないことである。多少の言い間違え、録音の順序など気にする必要はない。 覚えなくてはならないことを、片っ端から録音していく。このカセットテープは通勤・通勤時間などの隙間時間で繰り返し聞くようにする。 そして、学習が進んで復習の量が増えてきたら、2倍速で聞くようにする。この学習法で、全範囲の復習を短時間で行うことが可能になる。
これで、1日の学習は終了である。
そして、翌日の学習は、前日までの復習から始めること。前日だけの復習ではなく、必ず前日までの復習を終えてから、次の範囲に進んで欲しい。 つまり、前・・・前日→前前日→前日の復習をすべて行うのである。
具体的な復習法であるが、[行政書士肢別問題集」で既習範囲のすべての問題を解く。問題を間違えたり、理解が不足していると思えば、「郷原豊茂の憲法 まるごと講義生中継」や基本書の該当個所も読む。
前日までのすべての復習をすると、確かに時間がかかる。しかし、同じ範囲を繰り返し勉強しているうちに、当たり前になってくる知識も増えて、復習のスピードはどんどん上がるので、思ったよりは時間はかからないはずだ。 むしろ、1ヶ月後、2ヶ月後にまとめて復習をする方が、時間がかかる。前日までの復習を毎回する方がはるかに効率的である。 最終的には、「行政書士肢別問題集」で問題を見た瞬間に解答・解説が思い浮かぶレベルまで到達することが目標である。
まとめると、
「郷原豊茂の憲法 まるごと講義生中継」で内容理解→「行政書士肢別問題集」で知識の確認→「基本書」で知識を集約→カセットテープ録音→翌日に前日までの復習(「行政書士肢別問題集」で既習範囲すべての問題を解き、間違えたら基本書に戻って徹底的に確認)
という流れで進める。
このように同じ範囲を何回もオーバーラップしながら覚えていく(オーバーラップ学習法)。
■民法
民法は、とにかく1通り回すということが大切である。多少わからないことがあっても、先へ先へと進んでいく姿勢が民法を制覇するコツである。
まずは、行政書士講義生中継 民法 (行政書士一発合格シリーズ)
あとは、憲法と同じである。「行政書士 講義生中継 民法」で内容理解→「行政書士肢別問題集」で知識の確認→「基本書」で知識を集約→カセットテープ録音→翌日に前日までの復習、という流れで進める。
■行政法
行政法は、行政書士試験の中で最も重要な科目である。行政法を得意にしておけば、合格へ一気に近づく。 よって、他の科目よりも力を投入すべきである。
行政法は、法律用語や概念が難しい。そこで、まずは行政法入門
上記本を読み終えたら、行政書士講義生中継 行政法 (行政書士一発合格シリーズ)
あとは、憲法と同様である。「一発合格 行政書士講義生中継 行政法」で内容理解→「行政書士肢別問題集」で知識の確認→「基本書」で知識を集約→カセットテープ録音→翌日に前日までの復習、という流れで進める。
■商法
商法も他の科目と同様である。解説本は、行政書士講義生中継 商法・会社法 (行政書士一発合格シリーズ)
「行政書士講義生中継商法・会社法」で内容理解→「行政書士肢別問題集」で知識の確認→「基本書」で知識を集約→カセットテープ録音→翌日に前日までの復習、という流れで進める。
■多肢択一式対策・記述式対策
多肢択一式対策については、法律用語や概念を文章の中で覚えていくことが大切である。 オーバーラップ学習法は、解説本・基本書を何度も何度も読み込みながら知識を増やしていく。オーバーラップ学習法を実践すれば、多肢択一式問題に対応できる力が自然と身につくはずである。
次に、記述式対策だが、記述式といっても、問われている知識は択一式と何ら変わらない。よって、必要以上に恐れる必要はない。
記述式で問われているのは、条文、論点、手続きの流れなどの基本的な知識である。 しかし、ただ知識を知っているだけでは駄目で、事例に即して知識を運用する力(法的思考力)が求められている。
このような法的思考力を身につけるためには、知識の暗記だけではなく、知識の理解が必要不可欠となってくる。 記述式問題は、「やみくもに知識だけを丸暗記をしてくる受験生は、合格させない」という試験委員からのメッセージなのである。
オーバーラップ学習法は、知識の暗記のみならず理解を重視した学習法である。 理解→暗記→理解→暗記を繰り返していくので、 コツコツとオーバーラップ学習法を実践していけば、特別な対策をしなくても記述式問題に対応できる力がつくはずである。
そして、択一式問題で8〜9割正解できるようになったら、記述式対策の参考書を購入することをおすすめする。
記述式対策の参考書を使う目的は、どこに注意して記述式の勉強をすれば良いのかを把握することである。 くれぐれも、記述式対策の参考書を使って知識を覚えようとしてはいけない。知識の理解と暗記は、解説本・基本書・肢別問題集で行うこと。
記述式対策の参考書で、記述式で問われそうな個所を把握したら、基本書で該当個所をチェックしていく。 この頃には、択一式で8〜9割正解できるほどの実力がついており、ほとんどの知識は既に覚えているはずだから、時間はそれほどかからないであろう。
記述式では、不正確な知識は役に立たないことを肝に銘じて、正確な知識を徹底的に叩き込む。 そして、一度は自分で書いてみること。実際に書いてみると、記憶の不正確さに気づくはずである。 自分の弱点に築いたら、あやふやな知識がなくなるまで、知識の正確なインプットとアウトプットを繰り返すこと。 また、漢字の間違いにも注意して欲しい。
このように、オーバーラップ学習法をベースに、正確な知識のインプットとアウトプットを繰り返して勉強していけば記述式問題も恐れるに足らない。
■一般知識
一般知識の過去問だけは早い時期に1年分くらいは解いておいて欲しい。 というのも、一般知識(特に文章理解)は短期間で力をつけにくいため、あまりにも得点できていない場合は、早々に勉強を始める必要があるからだ。
具体的な学習法は、基本書を読んでから過去問を解くというオーソドックスな学習法でよい。あとは、予備校の模試や予想問題を活用しながら、対策を進めていって欲しい。
Copyright (C) 2007 行政書士試験リンク集 All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。
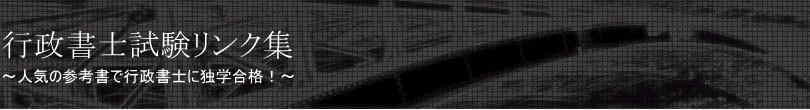
行政書士のおすすめ参考書を体験談を踏まえて詳しく紹介。
行政書士試験の新傾向の問題の試験対策、学習法も充実。
独学でも人気の参考書で合格を目指そう!独学学習プラン。
基本書、参考書、過去問の勉強法で行政書士試験に合格!
行政書士試験の新傾向の問題の試験対策、学習法も充実。
独学でも人気の参考書で合格を目指そう!独学学習プラン。
基本書、参考書、過去問の勉強法で行政書士試験に合格!
